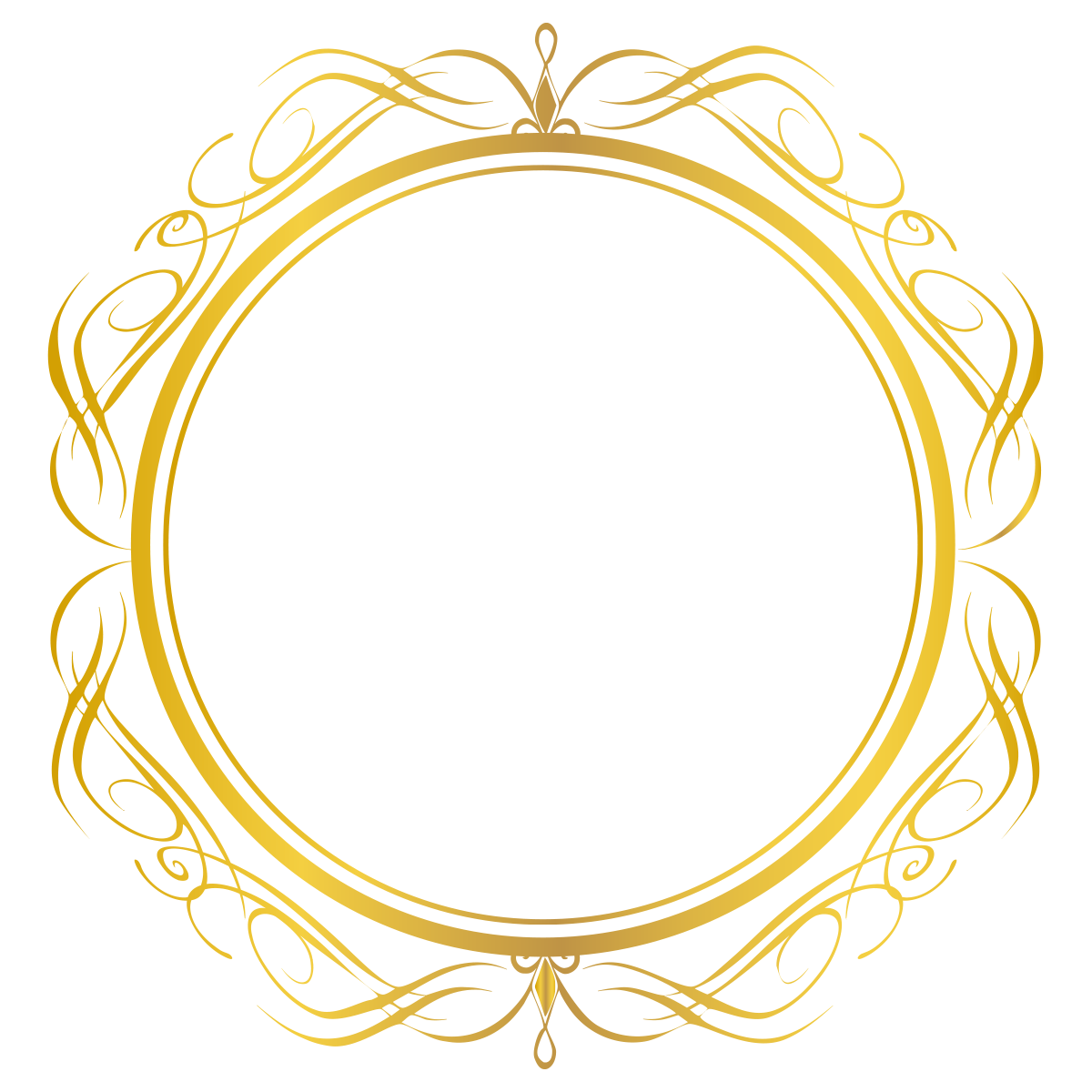Scene 1
「あれぇ〜、小エビちゃんじゃん、何してんの?」
頭上からそんな声が聞こえてきて顔をあげると、目の前にある立派な木の太い枝の上から、フロイド先輩が寝そべってこちらを見つめていた。
「フロイド先輩、こんにちは」
私がぺこりと頭を下げて挨拶すると、フロイド先輩はひらりと木の上から降りてきた。こんなに大きい人なのに、身軽だなぁと感心してしまう。
「あれ、小エビちゃん一人?アザラシちゃんは?」
「グリムは…エース達とハーツラビュルの談話室でおしゃべりしてますね…」
私を送り出した時の、ものすごいバカ笑いでひっくり返っていたグリムを思い出して、思わず顔が引き攣った。向かいに座っていたリドル先輩は呆れ返っていたし、トレイ先輩はものすごい苦笑いをしていたっけ。
「んでぇ、何してんのぉ?」
腰を折り曲げるようにして私の顔を覗き込んでくるフロイド先輩。やたらと背が高いから、私の目線に合わせるとどうしてもフロイド先輩は中腰みたいな体勢になる。それでもフロイド先輩は体が柔らかいのか、あまり辛そうな様子には見えない。
「私は、ちょっとお散歩しに行こうかと思って。フロイド先輩はなんでこんなところにいるんです?」
ここは学園から少し離れた森の手前。フロイド先輩は神出鬼没なところがあるけれど、それにしたって学園の敷地から外に出たところで会うなんて思っていなかった。
「オレはぁ、めんどくせーから授業サボってあちこちフラついてた〜。んで、眠くなったから昼寝してたぁ」
「そ…そうですか…」
なんて自由なんだろう…自由なのはいつものことではあるのだろうけれど、テキトーにふらついて学園の外に出てしまうなんて。ちょっとと言うかだいぶ驚いたけれど、フロイド先輩相手にいちいち反応していたらきっと疲れてしまうので、さっと流すことにする。
「あ、そうだ。暇なら先輩も一緒に行きます?」
ふと思いついてしまったので、思ったまま口に出してみた。私の言葉にフロイド先輩は怪訝そうに首を傾げる。こうやって話していると、ジェイド先輩と同じ顔ではあるけれど、フロイド先輩の方が表情豊かなような気がする。
「実はこれから桜を見にいくんですよ」
フロイド先輩が桜に興味があるとはとても思えないけれど、こうやって一人でお出かけするのも少し寂しいと思っていたところだったので、ダメ元で誘ってみるのもありかな、なんて思ったり。
「桜ぁ?そんなんあんのぉ?」
「トレイ先輩が教えてくれたんですよ。ちょうど今頃咲いてるはずだって。この森を抜けた先に一本だけあるみたいです」
トレイ先輩が描いてくれた地図をフロイド先輩に見えるように広げると、地図を覗き込んで、ふぅん、と興味なさげにつぶやいた。返事を聞くまでもなくわかる、これは断られるな、と。
「興味ねぇや〜」
「まあ、そうですよね」
予想通りすぎて残念な気持ちも湧かず、手元の地図を折り目通りに畳んでポケットにしまった。グリムやエースには少女趣味だって爆笑されたから、その反応に比べたらはるかにマシだ。ちなみにトレイ先輩とリドル先輩はもちろん笑ったりしなかったし、時間があれば一緒に行きたいと言っていたけれど、二人揃ってこれから用事があると言うことだった。
「つーかこの森、ゴースト出るらしいから、小エビちゃん一人じゃ無理じゃね?」
「ゴーストが出ないルートがあるみたいですよ。だからトレイ先輩が地図書いてくれたんですよ」
トレイ先輩は本当に面倒見が良くて素敵な先輩だ。部屋を出て行く瞬間まで笑い転げていたグリムやエースとは大違い。あいつらいつか絶対仕返ししてやるんだから。
そんなことを考えていると、フロイド先輩の顔が何故だか楽しそうに歪んで、ふぅん?とつぶやいた。なんだかとても含みのある言い方で、嫌な予感が頭をよぎる。この学園には性格に難がある人が多いけれど、その中でもリーチ兄弟は人の不幸を楽しんでいる節がある。今更ながら、自分の発言を後悔した。
「やっぱ俺も行こ〜」
ほらきた。思わず顔が引き攣ってしまいそうになるのをなんとか堪えた。リーチ兄弟がこう言う顔をしているときはろくなことにならない。
「で、でも、ただ桜見に行くだけで、そんなに面白くもないと思いますよ?」
「でもよく考えたらオレぇ、桜って本物見たことねぇし、どうせやることもねぇし」
「お昼寝はもういいんです?天気も良くて、絶好のお昼寝日和ですよ」
「もう3時間は寝たから眠くねぇし〜」
「そ、そんなに前からお昼寝してたんですか…」
それはもうお昼寝の域を超えているのでは、と思ったけれど、その言葉を言う前にフロイド先輩が私の背中をぐいぐい押してくる。うだうだいってないで早くいこーよ、なんて、ハートマークでもつきそうなほど楽しそうに笑っている。この人が何を考えているのかは流石にわからないけれど、きっと私にとってとてつもなく嫌なことを考えているだろうことはわかるので、あんなに楽しみでワクワクいていた気持ちが急速に萎んでいった。フロイド先輩、怖いです。
そんな感じで、フロイド先輩に押されるままに森の中に足を踏み入れた。
Scene 2
森の中では散々な目に遭わされた。せっかくトレイ先輩が地図を書いてくれたと言うのに、フロイド先輩の気分であっちこっち連れ回されて、しかもそれがことごとくゴーストの出る道で、驚かされたり追いかけられたり転ばされたり…その度にフロイド先輩はこれ以上ないほど楽しそうに笑って、ひとしきり楽しんだらゴースト達を締め上げて、あらかた片付けたら道の先へ進む。そんなふうにしていたら、予想していたよりもかなり時間がかかってしまって、桜の木にたどり着いた頃には陽が傾き始めていた。
心も体もヘトヘトだけれど、桜の木は満開で、とても美しかった。桜の木があるのは少し開けた小高い丘の上で、周りに他の木が一つもないせいか、なんだか特別な場所のように思える。学校から離れているせいもあって、こんなにきれいに咲いているのに人の姿は全くなかった。
言葉もなくぼうっと桜を眺めていると、フロイド先輩が隣にやってきて、私と同じように桜を見上げた。
「ふぅん。こんな感じか。女子が好きそー」
「はは、そうですね。フロイド先輩は興味なさそうですね」
「全く興味なーい」
言うと同時に、ふあ、と大きく欠伸をするフロイド先輩。先輩が桜に興味がないのは最初からわかっていたことだし、ここまできたのは単に私をからかって遊べると思ったからだって言うのもわかっていたことだ。気怠げに桜の根元まで歩き出したフロイド先輩を目で追いながら、ちょっとだけ寂しく思う気持ちを誤魔化したくて、無理矢理笑顔を作った。
「でもさー」
頭の後ろで両手を組んで気怠げに歩きながら、フロイド先輩が口を開く。その視線は意外にも桜の方に注がれていて、風にひらりと舞う花びらがなんだか妙にきれいに見えた。
「ミドルスクールんときのくそつまんねー遠足とか、小エビちゃんが一緒だったらもっと楽しかったんだろーなーとか思ったりすんだよね」
「え…そうなんですか?」
フロイド先輩が桜の根本にごろりと横になったので、その隣に人一人分くらいのスペースを開けて座る。チラとフロイド先輩に目をやると、また口を開けて大きなあくびをしていた。特徴的なギザギザの歯がバッチリ見えている。
「だってオレぇ、そもそも団体行動とか嫌いだし、きれいな景色とか課外学習とか全く興味ねぇし」
「ああ…まあそんな感じしますよね」
「そうそう。だからさぁ〜、小エビちゃんが一緒だったら小エビちゃんからかって遊べるじゃん?」
「…私ってそんなに面白いですかね。普通に生きてるつもりなんですけど」
なんというか…前々から思ってはいたけれど、リーチ兄弟も他の人たちも、この学園の人たちは私のことを遊び道具か何かだと思っている人が一定数いる気がする。リーチ兄弟に関しては特にそれがひどい気がするし、フロイド先輩はジェイド先輩よりかなりあからさまだ。嫌われるよりはいいのかもしれないけれど、あんまりぞんざいな扱いをされるのもちょっと切ないものがある。
「小エビちゃんはぁ、ちょ〜面白い。全然飽きないし、ずっと遊んでたい〜」
「…はぁ、それはどうも」
ちょっとムッとしてぞんざいな言い方になってしまった。まずかったかな、と思ってフロイド先輩の方に視線をやると、別に怒ったりはしていなくて、むしろにんまり笑ってこちらを見つめてる。
「もしかして怒ったぁ?」
「…いえ」
「そっかー、残念」
何が残念なんだろう、と内心ムッとしながらフロイド先輩から目を逸らす。そうやって桜を見上げると、せっかく見にきたのに全然桜を見ていなかったことに気がついた。全く、フロイド先輩と一緒にいるとどうにも調子が狂う。
「小エビちゃんってさぁ、オレのことケダモノか何かだと思ってない?」
「あれ、違うんですか?大体そんな感じだと思いますけど」
分かりきったことを聞くもんだから、ついまたムッとして返答してしまった。きっとこう言う反応もフロイド先輩を楽しませる要因なんだろうなとは思うけれど、この人相手だとなかなかうまく感情のコントロールができないから困る。
「これでもかなり抑えてるんだけどー」
そんなことをぶつぶつ言っているのをさっと聞き流して、満開に咲き誇る桜の木を眺める。やっぱりフロイド先輩の話はさっと聞き流すに限る。そうじゃないと、こっちの心が掻き乱されて仕方ない。
ひらりと桜の花びらが私の顔に降ってきて、咄嗟に目を瞑る。その瞬間視界の端にチラとフロイド先輩がうつったと思ったら、何かがのしかかってきて、体がぐらりと後ろ向きに倒れた。何かって言っても、この状況でのしかかってくるのなんて一人しかいない。慌てて目を開けると、目の前には案の定、フロイド先輩のにんまり顔があった。
「な、なんですか…」
「あはぁ、お望み通りケダモノになろうかなって」
そんなふうに気軽な感じでそういうと、あっという間にフロイド先輩の顔が近づいてきて、先輩の唇が私の唇に重なった。なんでとかどうしてとかそんな簡単な言葉はたくさん頭に浮かんでいたけれど、どれもこれも口に出せないまま、はむ、と唇を甘噛みされる。私が思ってたケダモノってそう言うことじゃないんだけど?なんてことも思ったけれど、どっちみち言葉に出すことはできそうになかった。
ケダモノなんて言った割にものすごく優しい唇が、やがて静かに離れていく。長い腕が肘をつくように私の顔に添えられて、大きな掌がびっくりするくらい優しく頭を撫でた。
こんなの、反則だ。何が反則だって、普段あんなに強引で乱暴なクセにすごく優しく触れてくるところとか、普段あんなに気怠げで冷たい目なのにまるで愛おしむようにこちらを見ていることとか。「女たらし」と言う言葉が頭に浮かんできたけれど、そんな言葉よりも先に恥ずかしさで顔が真っ赤になっていくのがわかって、両手で口元を覆った。その間もフロイド先輩はじっと私の目を見つめていて、頭がクラクラしてどうにかなってしまいそうだ。
「せ、先輩…近いです」
「近づいてんだもん、当たり前〜」
ちゅ、と音を立てて額に唇が触れる。フロイド先輩の髪が顔にふわりとかかって、ほんの少しだけ体がゾクッとした。
「か、からかわないでください…!」
「え〜?やだ。だっておもしれーもん」
そう言って楽しげに笑いながら、何度も顔や耳、首にキスをされて、その度に体がゾクゾクしてしまう。こんなのって卑怯すぎる。全然私の話なんて聞いて来れなさそうなのに、唇も頭を撫でる手もどこまでも優しくて、振り解くのがもったいなく感じてしまう。これもこの人の作戦なんだろうか。そうだとしたら、何ていう策士なんだろう。
名残惜しい気持ちをなんとか抑え込んで、フロイド先輩の肩をグッと押し離した。そうすると、ものすごく不満そうな顔のフロイド先輩と目が合う。
「こういうことは、その…恋人同士じゃないと、だめです」
「えー、何それ。つまんねー」
あからさまにむくれた顔でそう言われるけれど、こういうことは流されてするものじゃないと思う。体を起こしたフロイド先輩は、変わらぬ不満顔のまま私からぷいと離れていった。
怒らせてしまったなと思ったら、罪悪感がちくりと胸を刺す。だからといって続きをお願いしますなんていう気もないけれど、何かご機嫌が取れる言葉があれば…ご機嫌が取れなくても、不愉快とかじゃなかったですと伝える言葉があれば。そんな風に思って、思わずフロイド先輩の制服の裾を掴んでいた。
「…何?」
「あ…その…」
ちょっと冷たい声。顔を見なくても怒っているのがわかる。こうなると、ご機嫌をとるなんてことはきっと私には難しいだろうから、思ったことを思った通りに伝えるのがきっと一番なんだろう。…ちょっと勇気のいる言葉だけれど、なんとか震えそうになる唇を開いた。
「あの、頭撫でてもらえるのは…とっても、心地よかったです…」
「…」
フロイド先輩は何も言ってくれない。私の方も、こうやって口に出してみたらものすごく恥ずかしくて、次の言葉が何も思いつかない。二人でしばらく黙ったままでいると、少し強い風が吹き抜けて、桜の花びらが視界を横切っていった。
花びらを追って顔を上げる。視界の端に傾きかけたオレンジ色の太陽が見えたけれど、それを視界の真ん中におさめる前に、強く腕を引っ張られる。ぐらりと傾いた私の体は、そのまままっすぐフロイド先輩に抱き止められていた。
つまりこれは、抱きしめられたってことだ。そう認識できてしまったら、また強烈な恥ずかしさで顔が熱くなった。ものすごく背が高い先輩だから、胸よりも少し下のところに顔を埋める形になっていて、ぎゅうと私を抱きしめる腕は、痛いというほどではなかったけれど、身動きできないくらいには力強かった。
「あ、あの…フロイド先輩…?」
恐る恐る声をかけると、ハッとしたように私を離して、くるりと後ろを向いてしまう。その動作はなんとなく慌てているような気がしたけれど、先輩が慌てるような理由も特に思い付かなかったので、何事だろうと首を捻ってしまった。フロイド先輩は元々よくわからないけれど、今日のフロイド先輩はいつもよりさらによくわからない。
「もう飽きた。帰る」
吐き捨てるようにそういうと、振り返ることなくさっさと歩き始めてしまうフロイド先輩。足が長いせいかちょっと歩いただけですぐ遠ざかってしまって、あっけに取られた私は咄嗟に追いかけることもできず、ぼうっとその背中を見送ってしまった。
…と、思ったら、少しいったところで立ち止まって、くるりとこちらを振り返る。それから大股で私の方まで歩いてきて、何も言わずに、結構乱暴に私の手を掴んで、そのまま私の手を引いて歩き出した。私も引かれるままに、フロイド先輩の少し後ろをついて歩く。
これは、もしかしたら気のせいかもしれないけれど、こうやって後ろからちらりと見えるフロイド先輩の耳が、赤く染まっている気がして。さっきこちらに歩いてきたときのフロイド先輩の表情が、ものすごく照れたように歪んでいたような気がして。
なんだろう、なんだかすごく…胸がドキドキする。
繋いだ手が大きくて、優しくて。鏡なんかなくたって自分がものすごく照れた顔をしているのがわかって、今は振り向かないで欲しいと念じながら、大きなフロイド先輩の背中を見つめていた。
2021.05.10 monday From aki mikami