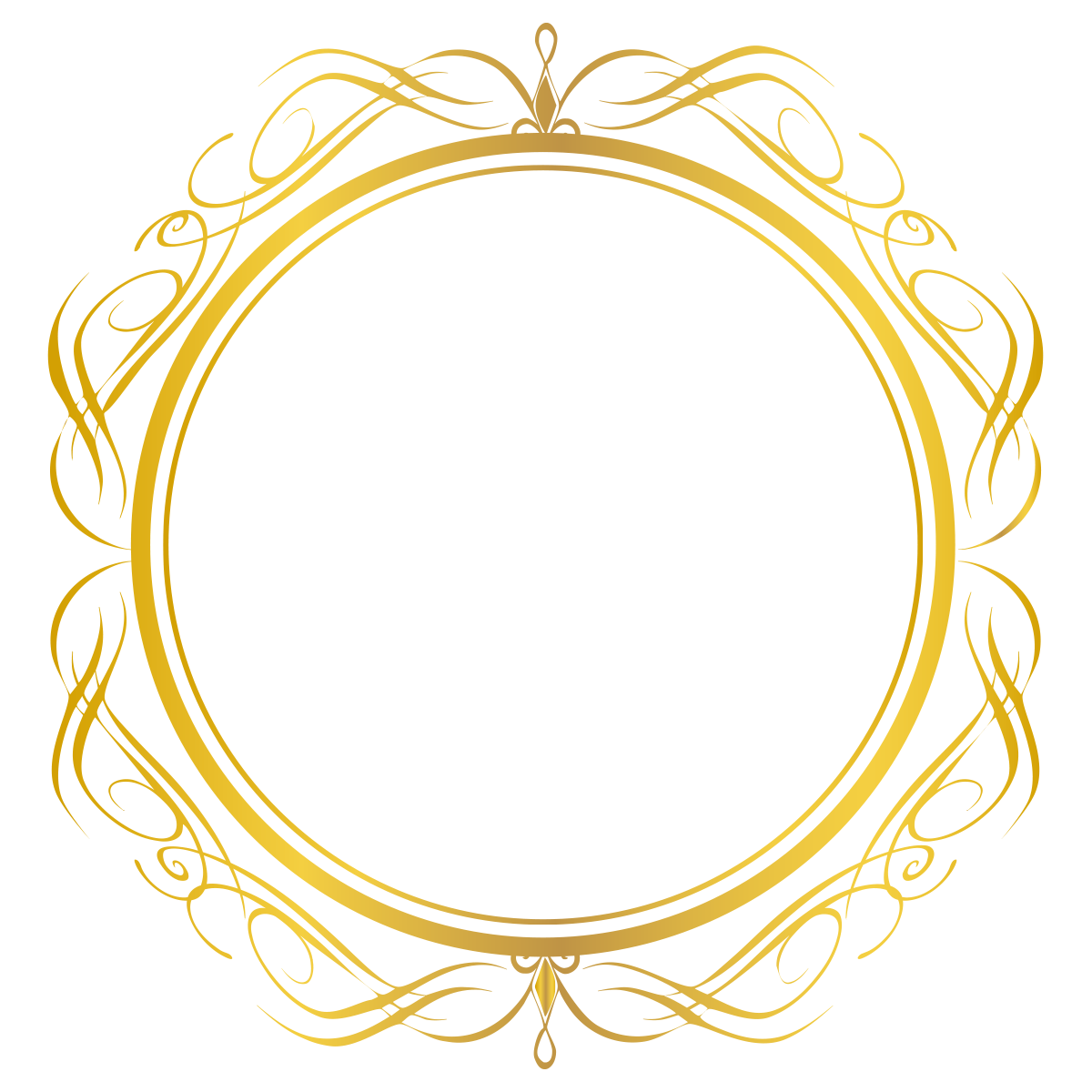Scene 1
「おや、さん」
そんな声が聞こえて振り返ると、これから入って行こうとしている森の手前に、ジェイド先輩がしゃがみこんでいた。…何やら、スマホを手にしているようだけれど。
「ジェイド先輩、こんにちは」
「こんにちは。どうかしたのですか、こんなところで」
悠然と立ち上がって穏やかな笑みを浮かべるジェイド先輩だけれど、側から見たら多分それを言われるのはジェイド先輩の方だと思う。…とは口に出さずに、私はかなり高い位置にあるジェイド先輩の顔を見上げた。
「実は、桜を見に行くんです」
「…桜、ですか」
ジェイド先輩は、長い指で顎を軽く触りながら小さく首を傾げた。きっとこんなところに桜があるなんて、ジェイド先輩も聞いたことがないんだろう。
「この森を抜けた先にあるらしいですよ」
「そうですか…それは初耳ですね」
「トレイ先輩が教えてくれたんですよ。この時期丁度咲いてるだろうって」
私の言葉に、ジェイド先輩はなるほど、と軽く頷いた。よく考えたら、ジェイド先輩でも知らないようなことを今年入ったばかりの私が知っていたら、疑問に思っても仕方ない。トレイ先輩から聞いたという言葉で納得してくれたんだろう。
「ところで、ジェイド先輩は何をしていたんですか?」
先ほどまでジェイド先輩がしゃがみ込んでいた場所を覗き込むと…何やら大きな石が置かれているようで。ジェイド先輩は顎に手を当てたまま、にっこりと笑った。
「その石の影、キノコが生えているんですよ」
「え?…あ、本当だ」
もともと見ていた角度からさらに首を傾けてみると、大きな石の裏側の方に、何やら白いキノコがたくさん生えている。そういえば、文化祭の時にもこういうのが趣味だといっていたなと思って納得してしまった。
「本当は採取して帰りたいところなのですが、今日は採取道具を何も持ってきていないので…こうして写真を撮っていたわけです」
自分のスマホをちらりと見せて悠然と笑うジェイド先輩。文化祭の時には確か「山を愛する会」って言っていた気がするけれど、まさか学園からすぐの森で活動をしているなんて、ちょっとびっくりだ。まあでも、本人は楽しそうだし、誰に迷惑をかけているわけでもないんだから、それはそれでいいんだろうと思う。
「あ、そうだ!ジェイド先輩も一緒に行きませんか?」
ふとそんなことを思いついてしまって、思ったままを口に出した。「山を愛する会」は山菜やキノコや花を鑑賞したりするって言っていたから、もしかしたら桜にも興味があるかもしれない。私の言葉に、ジェイド先輩はにっこりと笑った。
「貴方がよろしいのなら、ぜひご一緒させてください」
胸の前で丁寧に右手を揃えて、やんわりと笑いかけてくれるジェイド先輩。断られると思っていたわけではないけれど、受け入れてもらえたことにほんの少し胸を撫で下ろした。
「よかった。実はグリムとエースには少女趣味だって爆笑されてバカにされちゃって…」
「おや、貴方は女性なのですから、少女趣味であっているのでは?」
「…まあ、そうなんですけど」
おっしゃる通りではあるのだけれど、そう言われてしまうとなんだか少し悲しい。なんてことをちょっと思ったけれど、きっと面倒臭い押し問答になる気がしたので、口に出すのはやめておいた。そんな私にジェイド先輩は何かを察してくれたのか、特に先の言葉を促すこともせず、体をくるりと森の方へ向けて、何かを考えるように顎に手を当てた。
「ところで、この森はゴーストが出るのですが、貴方一人で入るおつもりだったのですか?」
ジェイド先輩の疑問はもっともだった。私は魔法が使えないから、ゴーストの対処ができない。ゴーストが出る森に一人で入るのは、本来ならとても危険なことだ。…けれど、今回の私には強い味方がある。ポケットからその「強い味方」を取り出して、ジェイド先輩に見えるように広げて見せた。
「ゴーストの出ない道があるらしくて、トレイ先輩に地図を書いてもらったんです!これの通りに行けば大丈夫だろう、って!」
「…なるほど」
とても含みのある声でそう言って、ニヤリと笑うジェイド先輩。…にっこり、じゃない。「ニヤリ」だ。嫌な笑顔に、薄気味悪さみたいなものを感じた。ギザギザの歯がちらりと覗いているところがまたいっそう恐ろしい。この学園には性格に難がある生徒が多いけれど、リーチ兄弟はその中でもとびきりヤバい部類に入る。ジェイド先輩はフロイド先輩ほどあからさまではないけれど、考えていることややることは似たり寄ったりだ。
なんてことを考えていると、ジェイド先輩はまた丁寧に右手を胸の前で揃えて、にっこりと笑顔を作った。
「僕もこの森には慣れていますので、道案内はお任せください」
「え…あ、っと」
「地図ばかり見て足元を見ていないと転倒する危険もありますし…僕なら、ずっと地図と睨めっこしていなくても、ある程度道はわかります」
「は、はぁ…」
申し出はとてもありがたいのだけれど、なんだか悪い予感しかしない。けれどその笑顔は有無を言わせぬ迫力があって、結構です、とはとても言えなかった。
「…じゃ、じゃあ…お願いします…」
「ええ、お任せください。…ふふっ」
その含みのある笑い方は何?と思ったけれど、聞いてしまうのは怖い気もしたので、仕方なく先に歩き出したジェイド先輩について森の中に入った。
Scene 2
森の中では散々な目に遭わされた。あっちに行ってもゴースト、こっちに行ってもゴーストで、驚かされたり転ばされたり追いかけ回されたり。トレイ先輩にもらった地図はジェド先輩に渡してしまっていたから、その道が正しい道だったのか間違った道だったのかもよくわからず、ただひたすらゴーストから逃げ回るばかり。その間ジェイド先輩はそれはもう楽しそうに私を眺めていて、やっぱり嫌な予感が的中したじゃないかと、ちょっと腹立たしい気持ちにもなった。まあ、結局最後は助けてくれるのだけれど、それまでが本当に長すぎる。そんなことを延々繰り返していたら思っていたよりもかなり時間がかかってしまって、桜の木についた時にはすでに陽が傾き始めていた。
心身ともに疲れ果てていたけれど、桜の木はとても美しかった。トレイ先輩が言っていた通り丁度満開の頃合いで、桜のいい匂いが風に運ばれてくる。周りに他の木がないせいかなんだか特別な場所みたいに見えて、傾きかけの夕日がスポットライトみたいになっているのが、より一層それを強調しているように思えた。
言葉もなくぼうっと桜を眺めていると、ジェイド先輩が私の隣にやってきて、同じように桜を見上げた。
「これが桜ですか。なるほど、美しいですね」
「あれ、もしかして先輩、桜見るのはじめてですか?」
「ええ。写真では何度か見たことがありますが、実物ははじめてです」
そう言って桜を見上げている横顔はなんだか穏やかで優しく見えて、普段感情が分かりづらいジェイド先輩だけれど、今は本当に桜を楽しんでいることがわかる。誘ってみてよかったな、と思ったら、自然と口元が綻んだ。
そうして改めて桜を見上げると、なんだか昔のことを思い出してしまって、つまらない話かもしれないと思いながらも我慢できずに口を開いた。
「私の住んでいたところでは、お花見っていう習慣があるんです」
「お花見?」
「はい」
お花見を知らないらしいジェイド先輩は、小首を傾げて私の方を振り向いた。海の中に花はないだろうから、お花見という単語が生まれなくても仕方ないのかもしれない。
「こうやって桜が咲いたら、何人かで集まってご飯を食べたり、あれこれおしゃべりしたりするんです。大人たちはお酒も飲んだり…ちょっとしたお祭りみたいな感じです」
「なるほど、それは楽しそうですね。それに、フロイドが喜びそうです」
「確かに、フロイド先輩は好きそうですね」
フロイド先輩が楽しそうに集まったみんなと戯れたりからかったりしている姿が想像できて、思わずふふっと笑ってしまった。ちらりと横見ると、もしかしたらジェイド先輩も同じことを考えていたのか、楽しそうに笑っている。夕日に照らされたその顔が、なぜだかいつもより綺麗に見えるような気がして、ほんの少しだけ胸が高鳴った。
「ジェイド先輩は、お花見みたいなことはしたことありますか?」
ちょっと照れくさい気持ちを誤魔化したくて、思いついた質問をそのままジェイド先輩に投げかける。ジェイド先輩は鋭いからもしかして気づかれていやしないだろうかと思ったけれど、先輩は口元に手を当てたまま、私の問いの答えを考えているようだった。
「そうですね…ミドルスクールの遠足や課外学習などはありましたが、家族や友人同士で集まってどこかに出かけるというのは、あまりなかったかもしれませんね」
「そうなんですか」
「ええ。そもそも僕たちが住んでいた珊瑚の海は深海の海。この桜のような華やかなものは、ほとんど存在しません」
「え…そ、そうなんです…?」
「ええ。太陽の光は届きませんし、食べ物も生食ばかりですしね」
「わ…ワイルドですね…」
一瞬、そのギザギザの歯で仲間の人魚に噛み付いているジェイド先輩を思い浮かべてしまって、思わず顔が引き攣ってしまった。普段はあまり意識することはないけれど、この人たちは人魚で、ウツボなんだ。
「ふふ。貴方には僕たちがケダモノのように思えるでしょうね」
「い、いえ…!そんなことは!」
心の中を読まれたような気がして、慌てて首を振って否定する。ジェイド先輩が本当にそんなことをしていたかなんてわからないのに、なんて失礼なことを想像してしまっていたんだろう。罪悪感で心臓がドキドキしている私に、ジェイド先輩はふふっと笑っていった。
「どうか気になさらないで。貴方たち陸の生物と比べると、僕たち海の生物は少し…そう、ワイルドなのは、事実ですから」
そう言って私の方を見るジェイド先輩は、嫌味っぽい感じではなかったし、ワイルドと言われたことを気にしたような様子もなかった。どちらかというと、私が慌てふためいている反応を楽しんでいるような…私をからかっているときの顔をしている。
…私が失礼なことに変わりはないけれど、本人が気にしていないならまあいいかとも思うし、何よりからかわれているのはなんだか釈然としなくて、ついムッとしてしまった。そんな私の反応に気づいただろうジェイド先輩は、もう一度ふふっと笑ったあと、ポケットからスマホを取り出して、桜の木に向けた。
「写真を撮りたいのですが、少々お時間をいただいてもよろしいですか?」
「あ、はい!それくらい全然!むしろ私も撮りたいので…!」
ジェイド先輩との会話のおかげですっかり忘れていたけれど、せっかくきたからには綺麗な写真を撮って、グリムとエースにエモいって言わせてやろうと思ってたんだ。私もポケットからスマホを取り出して、ジェイド先輩と同じく桜の木に向ける。
こうしてカメラを通して見てみても、やっぱり桜は綺麗だった。光と影のコントラストがより強調されて、哀愁が漂っているような感じさえする。こんな綺麗な景色を少女趣味だって笑い飛ばすなんて、あの二人はセンスがないなと思いながら、何回かシャッターを切った。きっとケイト先輩がいたら、すかさずマジカメにアップするんだろうな。そんな風に思ったら、ふといいことを思いついてしまった。
ジェイド先輩をみると、真剣な表情でスマホ画面を覗き込んでいる。どうやら何度か場所や角度を変えたりしながら写真を撮っているようだ。そんなジェイド先輩に歩み寄って行くと、私に気が付いた先輩がスマホ画面から顔を上げて私を見つめた。
「ジェイド先輩、一緒に撮りましょ!」
スマホのカメラを内カメラにしてジェイド先輩に向けて差し出すと、いいですよ、と返事が返ってくる。これでグリムとエースに先輩と桜見てきたよって自慢できる。拒否されなかったことに内心安堵しつつ、ジェイド先輩の隣に立って、スマホの画面に二人とも収まっていることを確認してからシャッターを切った。ケイト先輩がよく撮ってくれるおかげで自分から撮ることにはあまり慣れていないので、内心ちょっとドキドキしていたのは内緒だ。
「後でジェイド先輩にも送りますね!」
「ええ、お願いします。…いえ、やはり僕のスマホでも撮っても構いませんか?」
なんだか妙に改まった感じで言われたので、思わずジェイド先輩の方を振り返る。思ったより近い位置に顔があったのでちょっとびっくりしたけれど、写真を撮るのに改まる必要もないし、写真撮影に企み事も何もないと思ったので、いいですよ、と返事を返した。
ジェイド先輩が長い腕でスマホを持って、画面をこちらに向ける。画面内に顔がおさまるようにちょっとだけジェイド先輩の方に詰めると、もっと近寄ってください、と声がした。言われるがままに一歩近づくと、もっと、と言われて、また近づくと、もっとです、と言われて、もう十分じゃないかなと思いつつ一歩近づくと、もっと、と耳元で囁くような声がした。その声があまりに近すぎて、反射的にジェイド先輩の方を振り返った瞬間。
カシャリ、とスマホからシャッター音が鳴るのと同時に、ジェイド先輩の唇が私の唇に重なった。
何が起きたのか事態を飲み込めないまま、ジェイド先輩の腕が私の首元に回ってくる。この体制ならきっと中腰で辛いだろうに、そんなこと全く感じさせないくらい余裕のある動きで私の頭をやわやわと撫でて、額に、頬に、耳にキスをして、もう一度唇に啄むように触れて、最後にギザギザの歯で私の唇を軽く甘噛みして、静かに唇が離れていった。
なんで、どうして、なんのために。いろんな言葉が頭の中に浮かんでいたけれど、混乱してどれも口から出てこない。じっとジェイド先輩の目を見つめていると、逆光でほとんど影になった口元が意地悪に釣り上がって、ギザギザの歯がちらりと見えた。
「ケダモノになってみようと思いまして」
歯の間から赤い舌がぞろりと這い出して来たかと思ったら、また唇にちぅと吸い付かれて、少し体が震えた。離れた方がいいとも思うけれど、ジェイド先輩の腕が首に回されていて身動きが取れそうにない。…何より、ちょっと強引なキスも、嘘みたいに優しくなでてくれる手も、ものすごく心地よくて、離れたくない気持ちになってしまう。こんな風に流されるのは良くないと思いながらも、結局離れることができなくて、ジェイド先輩の制服の裾を軽く掴んだ。
やがて、静かに唇が離れていく。そのことを名残惜しく感じてしまってジェイド先輩の顔を見上げると、ジェイド先輩も私のことを見つめていた。いつも通りやんわりと、でもどこか、いつもより余裕のなさそうな笑顔で。
ジェイド先輩が中腰になっていた体を元に戻すと、自分よりもかなり高い位置に頭があることを実感する。ほとんど空を見上げるような角度でその顔を覗くと、私の頭のすぐ上でスマホを操作していて、画面を見つめたまま楽しそうに笑った。
「ああ、よく撮れていますね。ホラ」
そう言って見せられたスマホ画面には、ついさっき撮られたばかりの私とジェイド先輩のキスシーンがバッチリ写し出されていて、思わず発狂しそうになった。
「な…ななな!」
「ここまで綺麗に写っていれば、いいネタになりそうですね」
「え、ネタって…」
それはつまり、この写真があれば私のことをからかえるとか、いいように扱えるとか、そういう意味のこと?カッと頭に血が上って、ジェイド先輩のスマホに向かって勢いよく手を伸ばした。
「おっと、いけませんよ。僕にもプライバシーというものがありますから」
「私のプライバシーを先輩が侵害しようとしてるじゃないですか!」
「おや、そんなことはありませんよ。この写真は誰にも見せるつもりはありません。ええ、もちろんフロイドにも」
私の手では絶対に届かないところにスマホをあげられて、馬鹿みたいに背伸びをしようとするけれど、ジェイド先輩の片腕が腰を抱くようにして押さえ付けてくるのでそれ以上身動きが取れない。私なんかの力では当然ジェイド先輩の腕はびくともしなくて、何度か試してみても結局どうしようもなくて、なんだか馬鹿らしく感じてしまったら、すぐに全身から力が抜けていった。
すっかり脱力し切ってジェイド先輩の胸に顔を埋めると、ふふっと小さく笑った後、スマホを持っていた側の手が私の頭を優しく撫でる。一体スマホはどこに行ってしまったんだろうと思ったけれど、場所がわかったところでどうせジェイド先輩から奪えやしないので、それ以上考えることはやめておいた。
「…困りましたね」
こうなったら思い切り堪能してやる、と思ってジェイド先輩の胸に顔を押し付けていると、頭上からそんな声が聞こえてきた。様子を伺いたかったけれど、あまりに高い位置に頭があって、見上げるのは無理そうだったので、代わりにどうしました、と声をかける。なんとなくだけれど、ジェイド先輩の声がいつもより余裕がなさそうな感じに聞こえたので、無視をするのは憚られた。
それから、ややしばらくの沈黙の後、ジェイド先輩は静かにため息をついてから、口を開いた。
「もうすぐモストロ・ラウンジの開店時間なんです」
「え!先輩今日出番だったんですか!」
「ええ。そろそろ行かないと、間に合わなくなってしまいます」
「大変!すぐに戻らないと!」
大慌てでジェイド先輩から離れようとしたけれど、先輩は「そうですね」なんて答えながらも私を離してくれる様子がない。それどころか、私を締め付ける力がぎゅっと強まって、少しだけど痛い。ジェイド先輩の顎が私の頭にコツンと乗せられた後、頭を撫でていた手が、髪をかき分けるように後頭部全体を包み込んだ。
「…こうして触れてしまうと、名残惜しく感じてしまうものですね」
あまりに寂しそうにそんなことを言うものだから、私までさっきの離れがたい気持ちがぶり返してきてしまう。それに、私だけじゃなくジェイド先輩もそう思ってくれていることが、なんだかもうすごく嬉しい。口元が緩んでしまいそうになるのをなんとか堪えて、言葉の代わりに一度だけ頷いた。
「ですが、そうも言っていられませんね。もう行かなければ」
そういうと、あんなに強く抱きしめていた腕がするりと解けて、ジェイド先輩の体が離れていく。普段の私たちより近くにいるはずなのに、触れていないことがもう寂しく感じられてしまう。でもジェイド先輩のいう通り、そろそろ戻らないと。先輩のラウンジの時間もそうだけれど、あんまり遅いと、きっとグリムたちが心配する。
いきましょう、と言って歩き出すジェイド先輩の後ろをとぼとぼとついていく。頭では理解していても、寂しい気持ちを抑えるのはなかなか難しい。胸に顔を埋めた時のジェイド先輩の匂いがまだ鼻に残っていて、それがまた寂しさを増長させる。こんなに近い距離にいるはずなのに、たった一度触れてしまっただけでこんな風になってしまうものなんだろうか。
そんなことを考えていたら、ジェイド先輩が足を止めた。私もつられて立ち止まると、先輩はゆっくりと私の方を振り返って、静かに左手を差し出した。
これは、手を繋いで帰ろう、ということでいいのかな。そう思いながらおずおずと先輩を見上げると、夕日に照らされた先輩の表情が、なんだか見たことない表情をしていて。
差し出された手に静かに自分の右手を重ねると、また前を向いて、静かに歩き出す。繋いだ手が離れないように、指と指を絡ませながら。
これは、もしかしたら気のせいかもしれないけれど、私に手を差し出したジェイド先輩の顔が、照れたような表情に見えて。
どうしよう、すごく、胸がドキドキする。
繋いだ手の大きさとか、鼻に残る先輩の匂いとか、リアルに思い出せるキスの感触とか、色々なもので胸がはち切れそうになって、今だけは振り向かないでほしいと思いながら、先輩の横顔を盗み見ながら歩いた。
2021.05.13 wednesday From aki mikami.