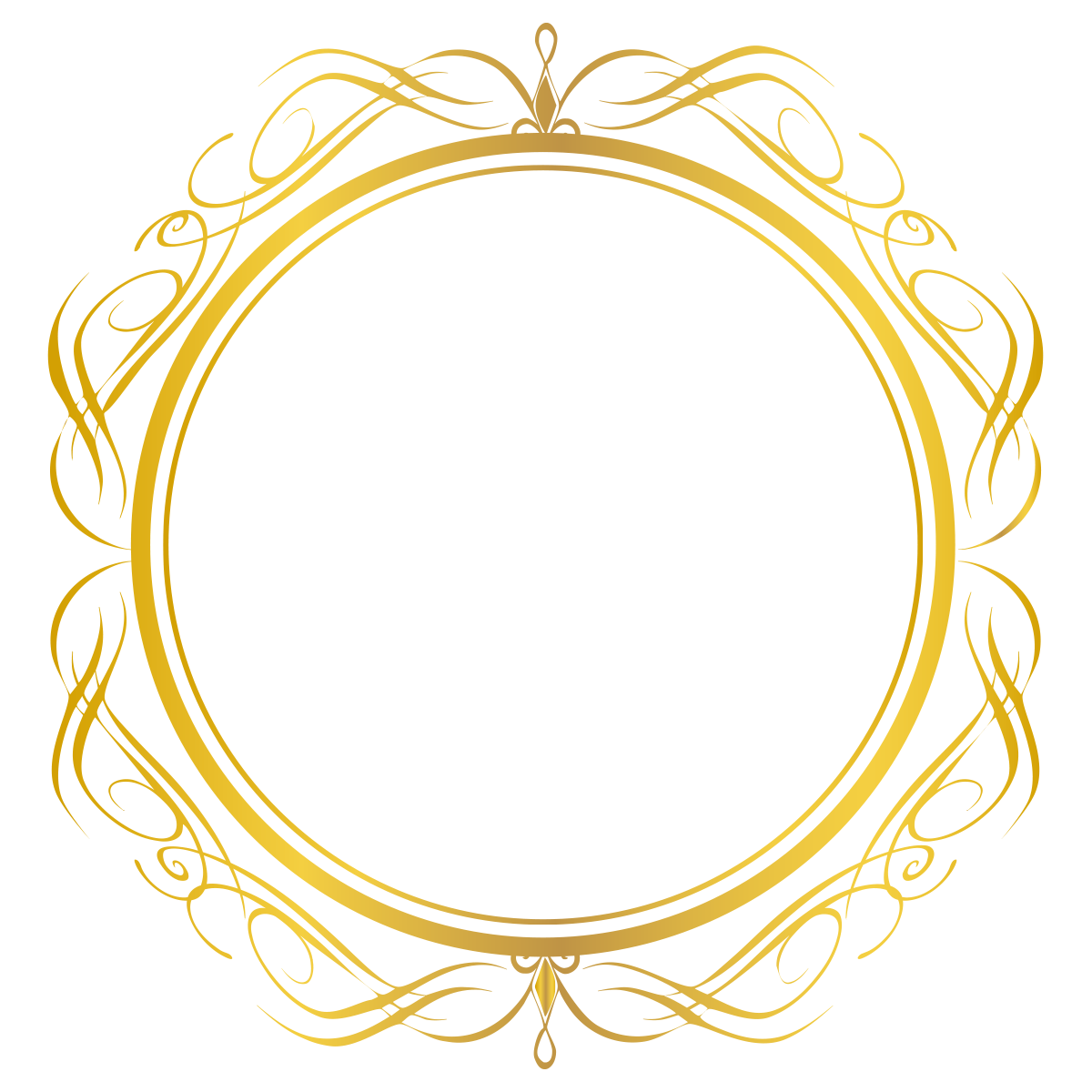Scene 1
いつものレッスン場で自分のダンスの完成度を確認しながら、さりげなく化粧や髪型が崩れていないかを確認して、ふぅとため息をついた。
久しぶりにヴィルの方から連絡が来たのは昨日のこと。私と一緒にダンスレッスンがしたいと言ってくれて、二つ返事でOKした。以前にも何度か一緒にレッスンをしたことがあって、ヴィルは元々センスがあるし、何よりダンスをより美しく見せるための角度や細かな手や足の動き、見ている人を魅了する笑顔や妖艶さは、私も学ぶところが多い。
…なんて理屈っぽい言葉を並べているけれど、つまり私はヴィルが大好きで、もっともっとヴィルと一緒にいたいから、こうしてヴィルと一緒にレッスンができることが嬉しかった。
ヴィルとの出会いは映画での共演だった。ネージュが主役でヴィルが悪役、そして私が悪役に連れ去られるヒロイン役。映画の中では主役とヒロインが結ばれるけれど、現実の私はヴィランにすっかり心奪われてしまった。それからヴィルと共演できる仕事があれば積極的に受けていたし、プライベートでも一緒に遊びに行ったりしていたけれど、最近は仕事でもプライベートでも全然会えていない。連絡するのも私ばかりで、向こうからは何も連絡してくれなくなった。もちろん送ったものに対してはきちんと返事をしてくれるけれど、もしかしたら避けられているんじゃないかと思ったから、昨日は向こうから連絡が来て本当に嬉しかった。
最近はネージュとの仕事ばっかりで、別にネージュの事が嫌いなわけじゃないけれど、正直うんざりしていたところだった。前にネットニュースや週刊誌で「ネージュと私が交際している」なんて嘘もいいところな記事が流れたけれど、あれはネージュがヴィルへの誕生日プレゼントを買うと言った私に強引についてきただけだ。でも、私とネージュをお似合いだという声が多いことに味をしめた事務所とマネージャーが、事あるごとに一緒の仕事を持ってくるようになって、最近では「音楽活動に専念したい」と嘘をついて、演技の仕事はできるだけ断ってもらってる。それでも強制的にやらされる演技の仕事は、やっぱりネージュが一緒だった。
誰も彼もみんな、私とネージュがお似合いだなんて無責任なことを言ってくる。私が好きなのはヴィルなのに。私の恋心を勝手に決めないでほしい。
そんなことを考えていると、レッスン場のドアが開く音がした。鏡の中の自分があまりにも怖い顔をしていたので、慌てて表情を作り直す。せっかくヴィルに会えるんだから、一番綺麗な私を見てほしい。
「こんばんは、ヴィル」
「こんばんは、。今日はよろしく」
さらりとかわす挨拶も、上品な微笑みも、美しい声も。いつも通りのヴィルだ。私の大好きなヴィル。
「こちらこそ、よろしく!ヴィルと一緒にレッスンするのはいい刺激になるから、すごく嬉しい!」
「アナタにそう言ってもらえると、アタシも嬉しいわ。アナタの歌やダンスは、アタシの目標とするところだもの」
ヴィルはいつもそうやって、私のことを褒めてくれる。ヴィルは嘘をつかないから、こうやって褒めてくれる言葉が本心から出た言葉だとわかる。そういうところが、ヴィルの大好きなところだ。いいことも悪いことも隠さずに、はっきり言ってくれるところ。
「それじゃあ、早速始めましょうか」
そう言って荷物を部屋の隅に置いたヴィル。その背筋の伸びた美しい背中に向かって、私は考えてきた言葉を口にした。
「あの、レッスンの前に…その、今度だす新曲を、少しだけ見てほしいの。少しだけ、行き詰まってるところがあって…」
私の言葉に、ゆっくりとこちらを振り返るヴィル。その、どこか探るような表情さえも、妖しく美しく見えて、わけもなくドキドキしてしまう。次に出す曲は、ヴィルのことを思って書いた歌詞だから、ヴィルに一番に聞いてほしいと思ったのが一番の理由だけれど、ダンスで行き詰まっているのも嘘じゃない。
じっと見つめ合っていると、やがてヴィルの口元がゆっくりと弧を描いて、タクトのように長くて美しい指が、静かに口元に添えられた。
「いいわよ。ただし、少しだけね」
「っ、ありがとう!」
嬉しすぎてはしたなくはしゃいでしまいそうになるのをなんとか堪えて、ヴィルに頭を下げた。間髪入れずに鏡の方を向いて歌い始める。ヴィルは時間の無駄を嫌うから、少しと言ったら少しだ。余計なおしゃべりをしている時間がもったいない。
鏡に映るヴィルをできるだけ視界に入れないようにしながら、歌い続ける。余計なことを考えていては、歌やダンスに悪い影響が出てしまう。とにかく今は、私ができる最高をヴィルに見てほしいから、歌とダンス以外のことは全て頭から放り出した。
Scene 2
「あら、もうこんな時間ね」
そう言ってヴィルが時計を見上げるので、私も釣られて時計に目をやった。あれからもう三時間ほど黙々とレッスンを続けていたらしい。
私の新曲については、少しだけなんて言いながらものすごく的確なアドバイスをもらって、それから歌とダンスのレッスンをそれぞれやって、その合間に今度VDCのオーディションの課題にする予定の曲とダンスを見せてもらった。VDCといえばかなり大きなイベントなので、毎年時間があればテレビでチェックしている。今年はヴィルの学校でやることは知っていたけれど、ヴィルが出場するなんて少し驚いた。
「そろそろ切り上げようか」
「そうね」
荷物の上に乗せていたタオルを取り上げて、汗を拭うヴィル。そんな姿すらすでに美しくて、思わず見惚れてしまう。やっぱりヴィルは、どんな時も綺麗だ。先ほどから…VDCの話を下あたりから、なぜだかいつもより浮かない顔をしているように見えるけれど、それでもやっぱり綺麗だ。私もタオルで汗を拭いながら、じっとヴィルの顔を見つめていた。
ヴィルは美しさを追求するためならなんでもする。そういう人だから、きっとストレスを溜め込んだりすることはあまりないはず。ネージュといるときはあからさまに嫌な顔をしている時があるけれど、それでもこんなふうに浮かない顔をすることはやっぱりない。珍しいな、とは思っていたけれど、何も話さないということはきっと私には聞かれたくないことなんだろう。…そう思うことにする。
今のヴィルはなぜだろう、なんだか近寄り難いオーラを発している気がする。
「…ねえ、ヴィル、このあといつものお店、寄って行かない?」
余計な考えを振り払いたくて、わざとらしいくらい明るい声でそういった。レッスン場の近くに美味しいオーガニック料理のお店があって、二人でレッスンをした後はヴィルと一緒によく食べに行っている。ヴィルも少し疲れているだけで、美味しいものを食べたりすればきっと元気になるはず。
そう思ったけれど、ヴィルは私の方を見ようとしないまま、冷たい声で告げた。
「やめておくわ。寮に帰ったら食事の用意があるもの」
「…そっか」
内心どきりとしていたけれど、なんとか冷静にそう答える事ができた。ヴィルは事実を告げているだけで、言い方がぞんざいなのもきっと疲れているだけ。だから、ムッとするのも悲しくなるのもなしだ。
さっさと帰り支度をしようとするヴィルにまた胸がどきりとしたけれど、努めて冷静に、且つ明るく話しかける。
「VDC、仕事の予定によってはスルーしちゃってたけど、今年はヴィルが出るんだからしっかりチェックしないとね。会場まで見に行っちゃおうかな」
「…あら、見たいのはアタシじゃなくてネージュの方じゃなくて?」
「…ネージュ?」
言葉の意味が分からなくて首を傾げていると、ヴィルが呆れたような顔で私の方を振り返ってため息をついた。
「今年のVDC、ネージュも出るのよ」
「そうなんだ…?」
「…アナタ、恋人なのにそんなことも聞いていないのね」
「…は?」
ヴィルの口からでた衝撃の一言に、私は表情を作るのも忘れてしまった。私とネージュが恋人?ヴィルは何を言っているの?
「アナタのマネージャーが言ってたわよ。ネージュとアナタは良い仲だって。それに二人で出かけたりしてるみたいだし」
「…ちょっとまってよ」
動揺とか怒りとか悲しみとか、色々な感情が湧いてきて、ヴィルの前だというのに笑顔が作れない。それどころか自分でもわかるくらい頭が熱くなって、顔がしわくちゃに歪む。最初は呆れ顔をしていたヴィルだったけれど、私の表情の変化に気が付いたのか、はっと息を呑んだ。
「二人で出かけたって…もしかして、ネットニュースのあれのこと言ってるの?」
「…」
「確かに最近ネージュとの仕事が多いけど、それはマネージャーが勝手に取ってくるだけ。ネットニュースだって、あれはデートじゃなくて、私がヴィルの誕生日プレゼントを買いに行くって言ったら勝手に着いてきただけ」
「…」
いつも強気なヴィルの顔が、困ったように歪むのがわかる。でも私の言葉は止められないし、止めたくない。よりにもよってヴィルに、そんな勘違いをされたくない。
「私はネージュじゃなくてヴィルと仕事したかったし、さっきの新曲だってヴィルのことを思って描いた歌だし、連絡だってヴィルとしかしてないし、ネージュと話す話題だっていつもヴィルのことばっかりだよ」
「…」
「私が好きなのは、ネージュじゃなくて…!」
「もういいわ」
私の言葉をピシャリと遮った強い声に、思わず肩が震えた。気がついたら私は泣いていて、ヴィルは鋭い目で私をじっと見つめながら、じりじりと私に近づいてくる。
急に怖くなった。こんなふうにはしたなく泣いて、ヴィルに嫌われてしまったんじゃないか。ヴィルは怒っているんじゃないか。…振られて、しまうんじゃないか。
私の目の前でヴィルが立ち止まる。怖くて顔を上げられないでいると、ヴィルの手が私に向かって伸びてくるのが見えて、反射的に両目を瞑った。そうすると、体が強く引き寄せられて、ヴィルの匂いと強い力に体が包まれる。
ヴィルに抱きしめられている。そう認識したら、恥ずかしさで顔がみるみる熱くなった。
「ヴィル!あ、あの私、シャワー浴びてないから!あせ、汗臭いよ!」
「そんなのアタシも同じよ。それに臭いなんて思ってないから、安心なさい」
腕の中で暴れる私に呆れたようにそう言って、ぎゅうと腕の力を強めるヴィル。そうされてしまったらそれ以上動くことができなくて、大人しくヴィルの腕に収まるしかない。抵抗を止めると、ヴィルは小さく息を吐いた後、私の肩に埋めるように顔を乗せた。
「アタシらしくないわね。本人に確かめもせずに、勝手に決めつけるなんて」
「…ヴィル」
「アナタを他の男に…よりにもよってネージュに取られると思ったら、はらわたが煮え繰り返りそうだったわ。問いただすことも、応援することもできず、…一番大切な言葉さえ、アナタに言わせてしまうところだった」
体が少し離れたと思ったら、ヴィルの綺麗な指が私の顎に添えられて、くいと顔を持ち上げられる。そのまま言葉を発する間もなく、ヴィルの唇が私の唇に重なった。
ほんの一瞬の出来事だったけれど、夢のような時間だった。ヴィルの方からこんなふうに私を求めてくれる日が来るなんて。静かに離れていった唇が名残惜しくてヴィルの顔を見上げると、ヴィルも同じように私のことを見つめていた。
「続きは、VDCが終わった後ね。今はVDCに集中したいの」
そういってヴィルは私から離れていくと、置いていた荷物を持ち上げて、首からかけていたタオルをその中にきれいに畳んでしまう。どうしたらいいか分からなくて呆然とその動作を見ていた私に、ヴィルは少し顔を向けて、どこか照れたようにふんわりと笑った。
「早くシャワー浴びて出るわよ。お店閉まるでしょ」
その言葉に、私はますます混乱してしまう。だってついさっき行かないっていったばかりなのに。でもその言い方はつまり、一緒に行ってくれるってことで…
「…まだ、一緒にいてもいいの?」
「いいも何も…帰りたいって言われたって、逃す気はないわよ」
そういうと私の荷物を持ち上げて、優しく笑いかけてくれる。その顔は今まで見たどんなヴィルよりもきれいで、格好良かった。
「うん!」
駆け寄って荷物を受け取ると、どちらからともなく歩きだす。そんな自然な距離感が心地よくて、やっぱり私はヴィルが大好きだなと心から思った。
2021.05.26 wednesday From aki mikami.